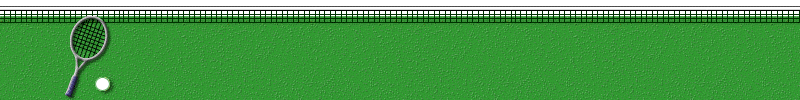日本ソフトテニス連盟の機関紙「ソフトテニス2009.11月号」の「歴史探訪」(財)日本テニス連盟副会長 表 孟宏氏 記事の抜粋です。
*****
現在、ソフトテニスで一般化されている陣形は、「雁行陣」といって後衛と前衛が専業の陣形であるが、この陣形もいろいろの変化を経て現在に至っている。
まず、「鶴翼陣法」と「魚鱗陣法」とに分けることが出来る。
「鶴翼陣法」とは、「蓋しこの場合に於いて中央線の右に落つる球は右方競技者、その左に落つる球は、背部競技者に一任するを可とする。この鶴翼陣法は容易かつ適当なる配備にして、最も普通一般の例なり。併し、ここに他の異れる陣法を張る人あり。即ちサーブ線の前方に落下する球は一人にて総て受合ひ、他の一人はむしろネットより遠くに距りて落つる球のみを打ち返へす。若し、競技者の一人が、バウーレイを得意とする時は、むしろこの魚鱗陣法に依るを良策とする」とあり、前者が並行陣で、後者が雁行陣といえるであろう。古い時代にはシュートボールが少なく、ロビング並行陣が主であったので、このように優雅な名称を持つ新しい戦法もあったようである。また、「底部並行陣」、「小雁行陣」、「大雁行陣」、「中部並行陣」、「単縦陣」などの名称の分け方もある。
「底部並行陣」は、2人ともベースラインにいて、打ち合うもので、1903(明治36)年ぐらいまでは、この陣形が普通の陣形になっていた。
「小雁行陣」は、1人がベースラインに、そして他の1人はサービスラインぐらいに進んで戦う陣形であり、「大雁行陣」は現在の陣形で、「中部並行陣」は2人ともサービスラインぐらいまで前進してプレーをすることをいう。また、「単縦陣」は最も変則的なもので、コートを縦に半分にしたその一方に2人とも陣取って打ち合う戦法である。
雁行陣といっても、現在のようにサービスやレシーブの時から前後衛に分かれているのではなく、当時は、ラリー中にチャンスを見てネットに前進してノーバウンドでボレーをしたり、スマッシュをしたりしたのである。
*****
この文章を読んで、思い出したのが、昨年狭山智光山で行われた、東日本選手権です。「篠原・小林」(日体桜友会ミズノ)は、向かうところ敵なし、とはこういうこと、という勝ち方でした。準々決勝、行徳・中尾(中央大学)、準決勝、松口・望月(ヨネックス、明電舎)をそれぞれ④-0、決勝の鹿島・中本(早稲田大学)には④-1で圧勝(3試合で12-1!)。後衛が積極的に前進攻撃をする「ダブルフォワード戦法」を採る、2人の凄まじい攻撃力の前に、雁行陣を敷くどのペアも、まさに、なすすべもなく、次々と敗れ去つていきました。「雁行陣の限界」と「これからの戦術の変化」を強く感じた大会でした。
1975年に始まった世界選手権。西田・時安、木之村・大木(埼玉)、井伊・稲垣、木口・横江、沖田・桜井(埼玉)、と日本は5回連続して優勝を飾りました。(この5ペアは中堀・高川より絶対強い、と私は信じています。)しかし、1985年以降、日本の優勝は、1995年第10回の北本・斉藤のみです。ソフトテニスの宗主国である日本は、トップの座を韓国に明け渡し続けているのです。その原因のひとつとなっているのが、韓国、台湾の「ダブルフォワード戦法」です。
現世界チャンピオンの韓国「金裁福・金煕洙」は、ダブル前衛による「ダブルフォワード戦法」です。
インドア大会や、国際大会では、管野(川口市役所)や中堀(NTT西日本)も積極的に前に詰めてきますが、日本のトッププレーヤーでは唯一、篠原・小林ペアがダブルフォワード戦法です。
道具はここ何10年の間に進化を遂げてきましたが、日本における戦術(雁行陣)に、変化はありません。いろいろな陣形が対抗していた明治時代の方が、柔軟性や、工夫があったと言えるかもしれません。
雁行陣同士の戦いで歯が立たなかったら、違う戦略で、という柔軟でフレキシブルな発想で練習している高校は、あるのでしょうか。
大会で、後衛が前に詰めてくるのは、川口総合と大宮の数ペアのみです。
ソフトテニス歴50年以上、今もジュニアなどの指導者としても活動している情報通で、「ソフトテニス専門店ラリースポーツ」社長の榎本さんに、ある時、次のような質問をぶつけてみました。
「なぜダブルフォワード戦法がもっと一般的にならないんでしょうか。」彼曰く、「2人とも相当運動神経がよく、オールラウンドプレーヤーでないと、なかなか機能しないんだよね。」とのこと。
「オールラウンドプレーヤー」 硬式テニスやバドミントンでは、当然の「目標」が、前衛後衛の専門化がルールのようになっているソフトテニスでは、目標を「オールラウンドプレーヤー」とするプレーヤーは稀でしょう。
他のラケットスポーツとの、この大きな違いはシングルス重視かダブルス重視か、にあります。ソフトテニスはその100年の歴史の中で、ダブルスのみを重視してきました。
シングルスにおいては、オールラウンドなプレースタイルが必要不可欠になってきます。ムダのない動き、素早いポジションへの戻り、広角に打ち分けるストローク、アプローチショット、ドライブボレー、スライスショット、ツイスト、もちろん、サービス、スマッシュ、ボレー。シングルスでは、テニスのすべての技術が要求されます。
前衛もサービスをするルール改正は、連盟の「オールラウンドなスタイルへ促す指針」というべきものだと思われます。また、ストリングは、「ネットプレーヤー向け」、「ストロークプレーヤー向け」、「オールラウンダー向け」の3種類に分類され、販売されています。その中でオールラウンダー向けが一番種類が多く売られています。この背景は何でしょう。
現在国際大会ではすべて、シングルス戦が存在しますが、大きな国際大会でのシングルス男子優勝者に日本人の名前は、過去1人もありません。
(ジングルス採用年/世界選手権1995年、アジア選手権1992年、アジア五輪2002年、東アジア選手権1997年)
団体戦にもシングルスが組まれていますので、日本連盟はシングルス強化に躍起となっています。直近の連盟理事会では、小、中、高団体戦にシングルスを導入するかが審議されています。
昨年狭山で行われた「第16回全日本シングルス選手権」は、早稲田大前衛同士の決勝戦となりました。風の影響もあったのでしょうが、迫力のかけらもなく、少しがっかりしました。しかし、強大なストローク力を持つ後衛陣に、徹底したスライスツイスト攻撃で勝ち上がってきた両者のオールラウンド力に、「弱い者が強い者に勝つコツ」を知るヒントがあるのかもしれません。
篠原・小林が天皇杯を奪取したり、高校の大会でシングルス戦が採用されるなど、何かのきっかけで、オールラウンド志向のダブルフォワード戦法ペアが一気に増える可能性もあると思います。
しかし、ソフトテニスプレーヤーの骨の髄までしみついている雁行陣が戦術の主役の座から降りることはないのではないでしょうか。
ただ、雁行陣をメインにしたオールラウンドなプレーが、今後どんどん増えていくのは間違いないでしょう。
熊田・横江で世界選手権3位など数々の戦歴を誇り、指導者としても、ナショナルチームのコーチ、監督、強化責任者であった、熊田章甫氏は、その著書「勝つためのソフトテニス熊田道場」の中で「戦う陣形の理想形」について、こう記しています。
「理想の陣形はまず、①ベースライン並行陣で守りながら、チャンスが来たら1人が前に詰めて②雁行陣に陣形を取り、攻撃。雁行陣で戦いながら、チャンスが来たら、2人とも前に詰めて、③ネット並行陣になり、攻撃します。このように、その場面、場面に適した陣形を取りながら、変化に富んだ攻撃をして戦うのが、理想形なのです。相手の特徴、状況を判断して使い分ければ、最高の戦術になるでしょう。」
以上
PS
1/6、関東高校選抜大会で武蔵越生高が初優勝、松山高が3位になりました。前号「2010年展望」、早くも当たりました!。我ながら自分の「眼力」にビックリしています。ハハハハ。
(笑ってばかりもいられませんね。春にはこれら2校に挑まなくてはいけないのですから。)
トップページへ戻る